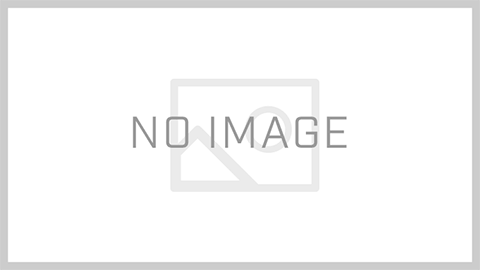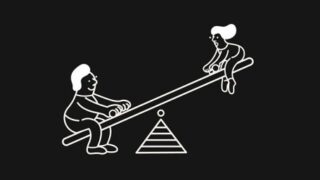現時点で、インハウス(社内)エージェンシーを有するマーケターは過去最大数に上り、インハウス化は業界の主流となっている。少なくとも、インハウス化に関するANAの最新報告書によれば、そうだ。インハウスマーケティングに関する議論では通常、迅速性、効率、管理統率の必要性が指摘される。とはいえ、すべてをインハウス化する動きに、幹部が皆、諸手を挙げて賛成しているわけではない。
「外部エージェンシーにしか、そして外部エージェンシーの規模とネットワークにしか提供できないことがいくつかある。私がそれと同じレベルに達しようと思えば、それこそ各々の専門部署を創り上げる以外にない」と、フリトレー・ノース・アメリカ(Frito-Lay North America)およびクエーカー(Quaker)のクリエイティブおよびデジタル部門VPクリス・ベリンジャー氏は話す。氏はフリトレーのインハウスクリエイティブエージェンシー、D3のトップでもある。
D3は最近、ポップコーナーズ(PopCorners)のスーパーボウル広告「ブレイキング・グッド(Breaking Good)」や、フリトレーがキャッチコピー「イズ・イット・コールド・サッカー・オア・フットボール?(Is It Called Soccer or Football)」を掲げて交わしたFIFAワールドカップにおけるスポンサー契約など、複数のキャンペーンを制作した。その一方で、フリトレーは同社ブランドのさまざまな分野に対応するべく、多くの外部エージェントとも仕事をしており、その数は十数社に上ると、ベリンジャー氏は話す。たとえば、PR企業ケチャム(Ketchum)にはコミュニケーション関連を、OMDにはメディアバイイングおよびアクティベーションをそれぞれ任せている。
この5年間で、D3のチームは2名のスタッフから現在の85名にまで成長を遂げ、アカウントストラテジー、ソーシャルメディア、クリエイティブ、プロダクション、マルチカルチャー関連の諸々を手がけている。
DIGIDAYは先頃、ベリンジャー氏に取材をし、社内と社外、両エージェンシーのバランスの取り方、AIに対する警戒心の高まり、そしてソーシャルメディアコンテンツ界の野獣であるAIをD3はどう飼い慣らすのかについて、話をうかがった。
なお、読みやすさを考慮し、発言には多少編集を加えてある。
――D3の成り立ちは? フリトレーの各ブランドのために担う役割は?
我々は完全なる内部エージェンシーであり、社のブランドチームと直に手を組んで事を進める。カルチャーに対する反応速度こそが、我々が誇る最大の利点だ。過去5年間、我々はD3という、完全なインハウス組織の構築および整備に尽力し、現在の形に文字どおり一から創り上げた。
モデルで言えば、我々はアドプション(適用)型だ。どこからも圧力はかからないし、外部エージェンシーパートナーとの仕事もやぶさかでない。というのも、すべてを社内で動かすのが良いとは思わないからだ。とはいえ、より多くのブランドにこの手法を採り入れてもらいたいし、ソーシャルキャンペーンや360°キャンペーン、コンテンツやその他諸々、我々が行なっていることに価値を見出してもらいたい。
The post インハウス 化が進むなか、フリトレーが賛成派・否定派いずれにも与さない理由 appeared first on DIGIDAY[日本版].
Source: New feed