
div style=”padding: 24px 24px 3px;margin: 24px 0;background-color: #eee;”>記事のポイント
- プライムデーはホリデーシーズンの消費傾向を示す重要な指標とされてきた。
- 高インフレと高金利が消費意欲を低下させ、価格重視の傾向が強まっている。
- 短いホリデーシーズンにより消費者は早期に買い物を済ませる傾向が増加している。
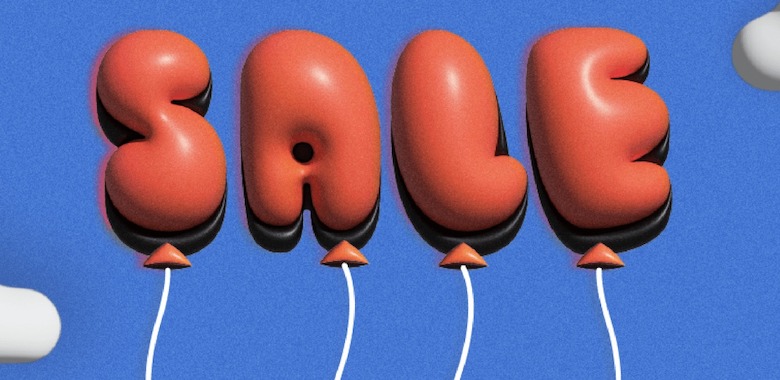

div style=”padding: 24px 24px 3px;margin: 24px 0;background-color: #eee;”>記事のポイント
プライムデー(Prime Day)は約10年前にはじまって以来、Amazonのeコマースビジネスだけでなく小売業界にとっても、特に重要なホリデーショッピングシーズンを前にして、今後を占う指標となってきた。
過去数年間、プライムデーの売上成長率は、ホリデーシーズンのeコマース売上を予測する際の判断材料として役立ってきた。市場調査会社のイーマーケター(eMarketer)によると、たとえば、2020年のプライムデーの売上成長率は42.8%で、ホリデーシーズンの38.1%増と同等だった。さらに、2021年と2022年もプライムデーとホリデーシーズンの売上成長率には相関関係があり、その率は1桁台後半から2桁台前半であったことも明らかにした。
しかし、ことしのホリデーシーズンは例年よりも短いホリデーカレンダーと米国大統領選挙をめぐる不確実性に加えて、終わらないインフレと高金利の影響も受けて厳しい状況にあり、プライムデーの数字は7月と10月のどちらも好調だったものの、簡単に指標として受け取ることはできない。続きを読む
The post 今年の Amazon プライムデーがホリデーショッピングの指標にならないかもしれない理由 appeared first on DIGIDAY[日本版].
Source: New feed