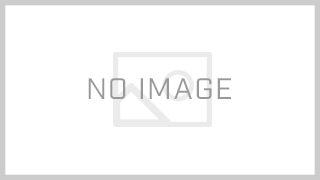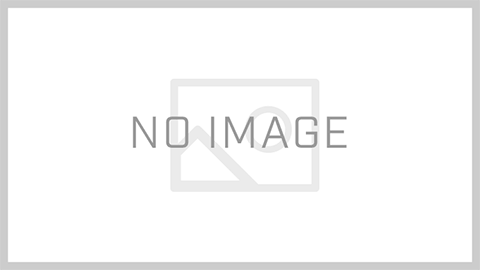小売企業が自社のリテールメディアネットワークの差別化を図るなか、「インクリメンタリティ」という用語が再び脚光を浴びつつある。
インクリメンタルリフト(増分的な上昇)を測定するというアイデアは、マーケターが長年にわたって注目してきたものだが、経済が悪化し、マーケティング予算が厳しくなるにつれ、インクリメンタリティという用語の使用が増えるようになった。特に、インスタカート(Instacart)からアルバートソンズ(Albertsons)に至るまで、ブランドが新興のリテールメディアネットワークに貴重な広告予算を使うように説得するため、セールストークの中でインクリメンタリティを強調することが増えているのだ。
たとえば、インスタカートは、インフォメーション(Information)によると、2022年に広告の販売で30%を超える収益を生み出したが、「インクリメンタリティのテストまたはリフト調査」が、広告サービスを構築する際に同社が重視する分野のひとつだと以前米モダンリテールに語った。インスタカートの広告商品担当バイスプレジデントを務めるアリ・ミラー氏は、インクリメンタリティが「広告主やブランドにとっては、広告によりどれだけ販売が促進されたか、実際の影響と原因の影響を示す、理想的な基準だ」と述べている。
同様に、アルバートソンズメディアコレクティブ(Albertsons Media Collective)の商品およびイノベーション担当バイスプレジデントを務めるエバン・ホボルカ氏は最近、チェーンストアエイジ(Chain Store Age)の取材に対し、小売企業が自社のリテールメディアネットワークで実施するキャンペーンの有効性を正当化するためにインクリメンタリティが役立つと語った。同氏は、「インクリメンタリティは、売上があったということだけでなく、その売上総額のうち、どれだけがリテールメディアネットワークでの広告の結果なのかということを示してくれる。たとえば、マーケティングキャンペーンの前には、ある商品に毎月10ドル(約1400円)を支出していた顧客が、キャンペーン後には毎月12ドル(約1680円)支出するようになった、というようなことを証明できる」。
しかし、インクリメンタリティテストに投資することは、プラットフォームやリテールメディアネットワークが広告主にアピールするための優れた方法であると広告主が主張しても、それは万能の解決策ではない。たとえばプラットフォームは、オフラインの世界にインクリメンタリティの指標を組み入れることが難しい。さらに、インクリメンタリティを測定するための汎用的で標準化されたフレームワークは存在しない。そのため、ブランドやメディアバイヤーはどのインクリメンタリティ統計を信頼するべきかを見極めるのが難しくなっている。
The post 【解説】「 インクリメンタリティ 」はなぜ今リテールメディア分野で人気のバズワードなのか? appeared first on DIGIDAY[日本版].
Source: New feed