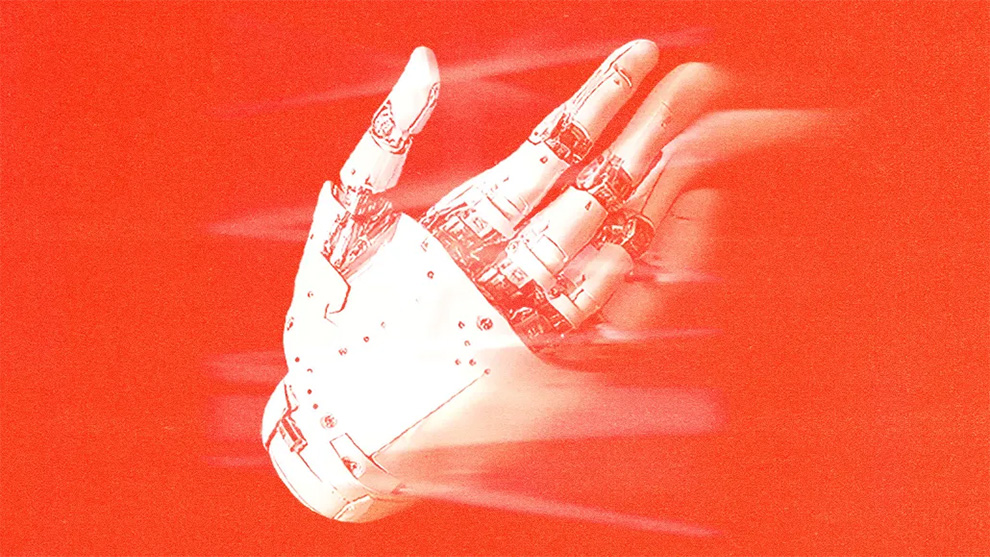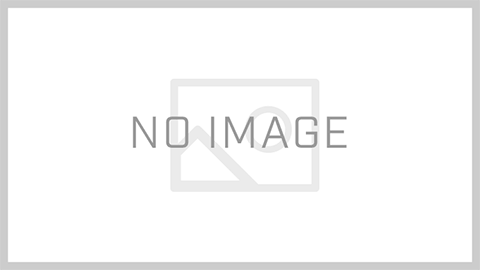- Amazonやウォルマートなどが、ユーザーの介入なしでタスクを実行できる「エージェント型AI」の導入を進めている。
- 「バイフォーミー」や「スパーキー」に代表されるAIは、従来のジェネレーティブAIから進化し、自動対応が可能になりつつある。
- 普及には信頼の確保が不可欠で、小売業者は正確な情報提供や検索最適化に注力している。
新たなAIのバズワードが登場した。
ここ数カ月で、Amazonやウォルマート(Walmart)などの大手小売業者が、エージェント型AIへの移行計画を発表している。
現在主流のジェネレーティブAIによるeコマースアシスタントとは異なり、エージェント型AIボットは、ユーザーの入力に頼らず自律的にタスクを完了できるという考え方だ。業界の専門家によれば、将来的にはエージェント型AIシステムがオンラインショッピング体験の標準となる見込みだという。
ただし、こうしたシステムが買い物客の検索傾向や商品発見の習慣を理解し、文脈を踏まえた判断を下せるようになるには、まだ数年はかかる見通しだ。それでも小売業者たちは、自社のAIボットを将来的によりエージェント型へと進化させるため、すでに投資をはじめている。
ウォルマートとAmazonのエージェント型AI戦略
フォレスター(Forrester)のエージェント型AIに関する最近のレポートでは、こうした「システムは知識経済の基盤となるだけでなく、組織の運営や競争のあり方を根本的に再定義することになる」と指摘している。
実際、ここ数週間の動きとして、ウォルマートは将来のパーソナルショッピングエージェントの実現を見据えた形で、エージェント型AIへの投資を発表している。
ウォルマートUSのCTO、ハリ・ヴァスデヴ氏は、「このテクノロジーはまだ初期段階にあるものの、ウォルマートではエージェント型の機能を迅速かつ計画的に事業全体の既存ワークフローに統合しつつ、小売の未来を形作る強力な機能を開発している」と語っている。
ウォルマートは6月初旬、ジェネレーティブAIアシスタントであるスパーキー(Sparky)を発表した。
スパーキーは、特定の商品に関するレビューを要約したり、おすすめ商品を提示したりできるが、将来的には、ただ情報を提供するだけでなく、顧客の購入履歴に基づいて、サービスの予約や商品の再注文などを代行するエージェント型AIとして進化することが期待されている。
類似の取り組みとしては、Amazonが最近試験導入を開始した「バイフォーミー(buy-for-me)」ボタンが挙げられる。これは、サードパーティのWebサイト上でも、顧客が商品を購入できるようにする仕組みだ。
AIの進化とエージェント型AIの定義
AIがより一般化するにつれて、その機能的な進化を表すさまざまなサブタームが登場してきた。ジェネレーティブAIとは、ChatGPTの登場とともに広まった用語で、特定のデータセットで訓練されたアルゴリズムを指す。これにより、ユーザーからのさまざまな入力に応じて、テキストや画像などのコンテンツを生成できる。
eコマースツールにおけるジェネレーティブAIは、多くの場合、商品を提案したり、レビューをスクレイピングして商品に関する質問に答えたりするアシスタントを指す。Amazonのルーファス(Rufus)やウォルマートのスパーキー(Sparky)などがその代表例だ。
これに対して、エージェント型AIはここ数カ月で注目されはじめた概念であり、アシスタントがフォローアップの質問やユーザーの介入なしに自律的に行動できるようになることを意味する。
[▼会員登録をして続きを読む▼]
The post Amazonやウォルマートも導入 エージェント型 AI の実力と課題とは? appeared first on DIGIDAY[日本版].
Source: New feed