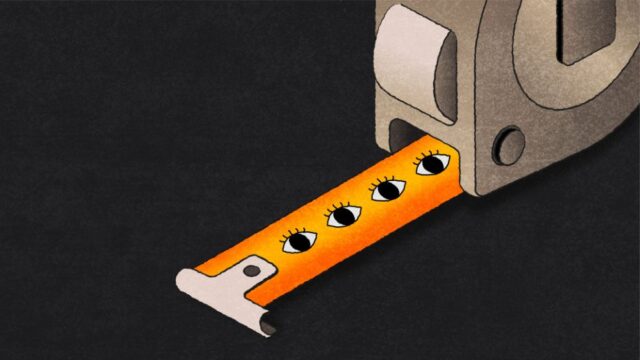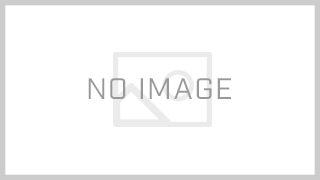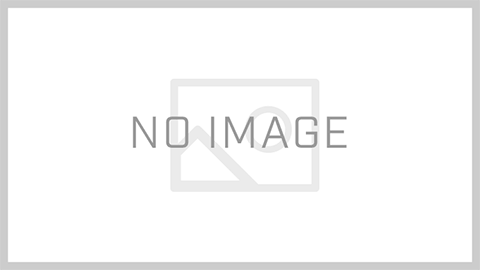- AIブラウザの普及により、パブリッシャーの検索流入が減少し、従来の収益モデルにさらなる圧力がかかっている。
- AIアシスタントがユーザーの行動を代行することで、価格比較や旅行検索などの行動型サービスに直接的な影響が出る可能性がある。
- パブリッシャー側は、AIエージェントによる有料アクセスなど新たなマネタイズ手段を模索しはじめており、収益化の機会と捉える声もある。
AIブラウザ争いは、AI検索ツールによるリファラルトラフィックの減少に苦しむパブリッシャーにとってどんな影響を及ぼすのか。AIブラウザは、従来の検索トラフィックをさらに押し下げる可能性があり、パブリッシャーは、AI企業から新たな収益を得る道を模索する必要に迫られる——そう各社幹部たちは口を揃える。
実際、Googleは「ディスカバー(Discover)」にAI要約機能を導入し始めており、これによってパブリッシャーはリファラルの導線からさらに遠ざけられる懸念がある。
一方、AI企業パープレキシティ(Perplexity)が新たにリリースしたAI搭載ブラウザ「コメット(Comet)」や、オープンAI(OpenAI)によるブラウザが近いうちに公開されるとの見通しは、メディア業界に戦々恐々とした空気をもたらしている。
パープレキシティの発表によれば、コメットは「従来のブラウジング体験をシームレスで会話的な体験へと変えるAIブラウザ」であり、タブやアプリを切り替えることなく、ユーザーが「思考を声に出して伝えるだけで」、リサーチや製品比較、メール送信、ミーティングのスケジューリングといったタスクを代行できるという。
コンテキストを理解し、複雑なワークフローを単一のインテリジェントなインターフェースに統合することで、これを実現するとしている。
米Digidayによるコメットのテストでは、ブラウザはGoogleのChromeと似た検索バーを備えたホーム画面からはじまり、「全タブを閉じる」、「最近のメールを要約する」といったタスクも実行可能だった。さらに、ウェブ閲覧中に表示可能なAIアシスタントを備え、常にユーザーをサポートする仕様となっている。
こうしたエージェント機能が未来のブラウジング体験の中核になることに期待を寄せるパブリッシャーも存在するが、一方で、ブラウザがコンテンツアクセスを支配するようになれば、破壊的な影響を及ぼすとの警戒も根強い。
[▼会員登録をして続きを読む▼]
The post AIブラウザ によって消えるユーザーの習慣 メディアに迫られる収益構造の再編 appeared first on DIGIDAY[日本版].
Source: New feed