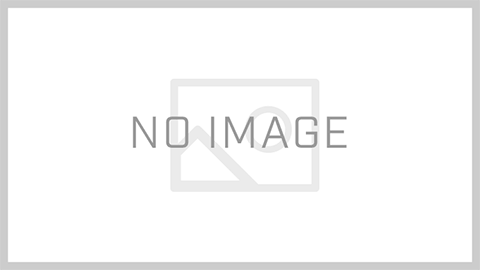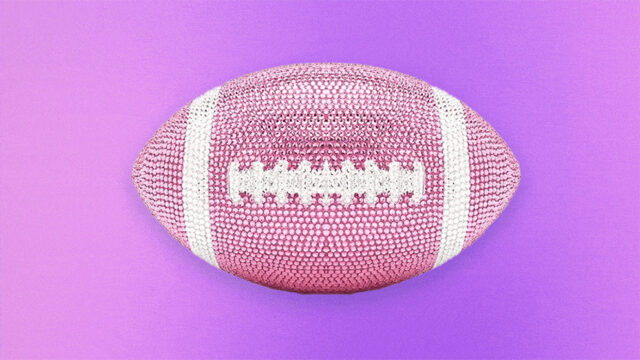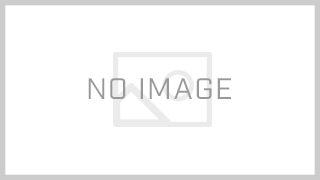- AIを利用した政治的マイクロターゲティングに対する懸念が高まり、大手テック企業をはじめ、連邦議会や欧州委員会も対策を検討している。
- たとえば、Metaは外部プラットフォームからのAI画像に対するラベル付けの計画を発表し、Googleは「コンテンツの来歴と真正性のための連合(C2PA)」の運営委員会に参加するなど、AIコンテンツ標準の採用に注力し始めた。
- しかしながらディープフェイクの広がりに関して、もとを辿れば大手テック企業が運営するプラットフォームやツール自体が重要な役割を果たしているのではとの指摘もある。
AIプロバイダーや政府機関は2月上旬、AIが生成する誤情報からインターネットを守ることを目的とした取り組みを相次いで発表した。
メタ(Meta)が外部プラットフォームからのAI画像にラベル付けするための詳細な計画を発表した数時間後、オープンAI(OpenAI)がChatGPTとDALL-E用APIによって生成された画像にメタデータを含めることを開始すると発表。さらにその数日後、Googleはさまざまな種類のAIコンテンツに関する基準を設定する重要なグループである「コンテンツの来歴と真正性のための連合(Coalition for Content Provenance and Authenticity:以下、C2PA)」の運営委員会に参加すると発表した。
Googleはまた、「コンテンツ・クレデンシャルズ(Content Credentials:CC)」のサポートも開始する。それは、C2PAと「コンテンツ認証イニシアチブ(Content Authenticity Initiative:CAI)」によって作成されたAIコンテンツである「(食料品に付けられる)栄養表示ラベル」のようなものだ。なお、2019年にCAIを設立したアドビ(Adobe)は、2023年10月にCCのメジャーアップデートを発表している。
主要な配信プラットフォームの参加
このアップデートは、主要な配信プラットフォームを標準化プロセスに参加させるという、いくつかの面で特に注目に値するものだった。プラットフォームレベルの参加は、AI標準のメインストリーム採用を促進し、コンテンツが本物か偽物かを見分ける方法を人々がより良く理解するのにも役立つだろう。加えて、企業、研究者、さまざまな政府機関の連携も必要だ。CAIのシニアディレクターであるアンディ・パーソンズ氏は、「Googleのような巨大企業の参加は、インターネットの情報エコシステムを改善するために必要な『雪玉効果』をもたらすのに役立つ」と述べた。
主要なAIモデルプロバイダーがC2PA標準を設計・使用していることも、コンテンツ制作と配信の両プラットフォームで統一的な採用を促進するのに役立っている。パーソンズ氏は、アドビのFirefly(ファイヤーフライ)プラットフォームは、昨年発表された時点ですでにC2PAに準拠していたと指摘する。
同氏は米DIGIDAYの取材に対し、「モデルプロバイダーは、どのモデルが使われたかを開示し、必要がある場合、自社のモデルが何らか(それがニュース価値のあるものであれ、有名人であれ、そのほかの何かであれ)を生み出したかどうかを判断できるようにしたいと思っている」と語る。
選挙への影響がきっかけに
政府機関もまた、AIが生成する誤情報を防ぐ方法を模索している。米連邦通信委員会(FCC)はこのほど、ジョー・バイデン米大統領に似せたAIディープフェイクのロボコールの登場を受け、AIが生成した音声によるロボコールを禁止し、電話消費者保護法(Telephone Consumer Protection Act)の下では違法とした。一方、ホワイトハウスは多数の大学、企業、その他の組織を含む200以上の組織が新たなAIコンソーシアムに参加したと発表。さらに欧州委員会(The European Commission)もまた、選挙の完全性に関するDSAガイドラインのために意見を集めている。[続きを読む]
The post GoogleやMetaが AI コンテンツ「標準化」へ本腰。ディープフェイクに歯止めはかかるのか appeared first on DIGIDAY[日本版].
Source: New feed